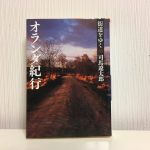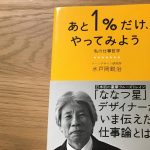「家を出るとき、右足から出るか、左足から出るかで、その後の人生は変わるのだろうか」
高校生の頃、駅へ向かって歩きながら、そのことについて真剣に考えたことがある。右足の一歩と左足の一歩、歩幅はわずかに異なるはず。だから、その小さなズレが、いずれ大きなズレとなって、人生に影響を及ぼすかもしれない。
「たとえば今、下を見ていなかったら踏み潰していたかもしれないこのアリが、無事に生きられたことで、回り回ってその後のぼくの人生に何か影響は及ぶのだろうか」
その疑問はあまりにもバカバカしくて、誰かに聞いてみようなどとは思わなかった。
しかし、高校3年生のときに偶然読んだ本で、ぼくの疑問はそこまで馬鹿げていなかったことを知った。
『カオス―新しい科学をつくる』という本だった。
どうやら20世紀に生まれた「カオス」という学問によると、「バタフライ効果」なるものが存在し、たとえば「今日の北京で1匹の蝶が空気をかき混ぜれば、翌月のニューヨークの嵐が一変する」のだという。それを読んだ瞬間、冒頭の疑問を思い出したのだ。
カオスの最も大きな特徴は、「初期値に対する鋭敏性」にある。すなわち「最初の状態がほんの少し違うだけで、将来非常に大きな違いを生む」というものだった。身近な例では、天気予報の技術に応用されている。
ぼくはこの未知の学問に心を躍らせた。一時は真剣にカオスの研究者になりたいと思い、横浜国立大学の後期試験の面接で、「カオスの研究をしたい」と熱く語り合格した。結局早稲田を選んだが、入学していたら全く違う人生になっていただろう。
だけど、カオス的な考え方は、今も変わらずぼくの中にある。「何も起こらないかもしれない。でも、何かが起こるかもしれないから、行ってみよう、やってみよう」という考え方だ。
目の前で困っているおばあさんに手を貸しても、道に落ちているゴミを拾っても、掃き掃除をしているおじさんに「おはようございます」と声をかけても、今日のプレゼンが上手くいくとは限らない。でも、この世界の全ては、目に見えない何かで繋がっている気がする。
たとえ今がうまくいっていなかったとしても、そんなのはどうだっていいことだ。思うようにいかない、やりたいことができない。そんなことは、誰にだってある。人生に理不尽・矛盾はつきものだ。今日もどこかで蝶が舞っている限り、未来は誰にも予測できない。いつかきっとうまくいくから、現状は気にしなくていい。
だけど、好奇心の灯だけは、消しちゃいけない。大人になると、もう新しい知識はなくても、器用に生きていくことができる。
でも、新しい発見のない人生なんて、楽しいだろうか。無難に生きて、何が生まれるっていうんだ。好奇心が湧かないときは、海外に出たらいい。常識の通用しない世界では、否が応でも健全な好奇心が息を吹き返す。
知っているようで、よくわかっていないことがたくさんある。
コーヒーの「ドリップ」って何? インカ帝国はどうして滅亡したの? ナスカの地上絵はどうやって描かれたの? 飛行機運賃ってどうしてこんなに高いの? スイカは果物?野菜? どうして君はそんなことまで知っているの? オリンピックに出るってどんな気分? その小説のアイデアはどこから湧いてきたの? どうして歌手になろうと思ったの? スコールズのミドルパスはどうしてあんなに精確なんだろう? ビールってどうやって作るの?
そんなこと聞くなんて、馬鹿げてるって言われるかもしれない。でもカオス理論も、天気予報も、もっとridiculous(バカバカしい)な考えから生まれたんだ。他人のridiculousなアイデアに、ぼくらは恩恵を受けているんだ。今更聞いたっていいじゃないか。確かに昔習ったかもしれない。聞いたかもしれない。でもそのときは興味がなかった、覚えていない、ただそれだけのことだ。
脈絡はいらない。自分が抱いた素朴な疑問を無視しないでほしい。ほかの誰かが、必ずしも同じ疑問を抱くとは限らない。誰にだって間違いはある。勘違いもある。抱いた疑問は、本当にバカげていることの方が圧倒的に多い。でも、世界はそこから動いてきた。人の好奇心は誰にも否定できない。
新潮社
売り上げランキング: 245,480