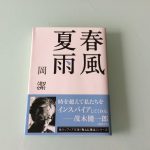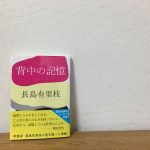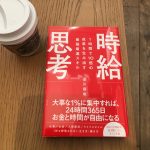昨日、『君たちはどう生きるか』という本を読みました。
毎日本屋さんへ行くので、以前から話題になっていることは知っていました。でも、ただの流行本だと思って、長らく読もうともしませんでした。
しかし、ふと気になって数ページめくり始めたら、止まらなくなり、一気に読み切ってしまいました。色々な感情が湧き上がり、最後は涙目になりました。
読む人によって感じることは異なるでしょうが、感想をひとことで言うと、「人と人の、心の通った手紙(言葉)のやりとりは尊い」ということ。
そして無性に悔しくなったのは、ぼくもかつては主人公のように、よく悩み、純粋で、まっすぐな生き方をしていたのに、いつからか、「妥協」するようになってしまったこと。
「社会はこういうものだ」「人生はこういうものだ」という、諦めのような感覚に、徐々に蝕まれていった。
「大きな挑戦をして、社会に影響を与える人間になりたい」とも思っていました。でも、何かをやるたびに、後ろ向きな言葉もかけられたりして、少しずつ挑戦することが億劫になったり、恐れを感じるようになってきました。そんなとき、「まあまあ、このくらいでもいいかな」と妥協したくなることがあります。
どうしてこうなってしまったのか、どうしたら以前のような気持ちに戻れるのか、あるいは戻る必要があるのか、ないのか、色々考えることがあります。
そしてこの本を読んだとき、少なくとも過去の自分の習慣の中に、この先に進むヒントはあるなと感じます。何か新しい能力が必要なわけではなく、ただ思い出せばいい。
小綺麗な文章を書くだけではなく、自分の心で感じたことに対して、もっと素直に、もっと泥臭く向き合っていこうと思います。そんな気付きを与えてくれる本でした。